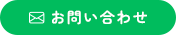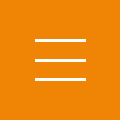お彼岸の歴史
お彼岸の歴史
お彼岸はインドのサンスクリット語「パーラミター」を中国語で「到彼岸」と漢訳した「彼岸」を略した言葉です。「彼岸」とは悟りの世界を表し、それに対して「此岸(しがん)」は現世、迷いの世界を意味します。春分の日、秋分の日を中日(ちゅうにち)として前後3日間(合計7日間)で行われる日本独自の仏教行事です。中日は1年のうちで昼の長さと夜の長さがほぼ同じになります。
1つのお話をご紹介します。西暦806年に日本初の彼岸会が行われたようです。これは藤原種継暗殺事件の関与を疑われ、配流の途中で無実を訴えながら絶食をし、憤死した早良親王の(祟りを鎮める)為に行なわれた出来事です。諸国の僧が7日間、昼夜を問わずお経を読誦するよう命じられ行われたのです。このことが現代のお彼岸の起源といわれています。
早良親王は桓武天皇の弟にあたる人です。兄である桓武天皇が天皇に即位すると同時に皇太子になっています。桓武天皇は即位当時45歳と老年ともいえる年齢でしたので早良親王が立太子された状況でした。
こういったことから公家や武士の間で彼岸の時期に追善供養を勤めることが盛んになり今日のお彼岸の行事につながっています。
また、平安時代の文学や芸術は、仏教の影響を強く受けており、特に『源氏物語』や多くの和歌にもお彼岸にまつわる表現が見られます。貴族たちが仏教の教えを生活の中に取り入れることが多く見られるようになりました。
また江戸時代には商業の発展と共に庶民の間でもお彼岸の風習がより広まりました。庶民が手軽に集まることができるようになったため、お彼岸の行事が広まったのです。江戸時代の文化は町人や農民たちの間で浸透し、地方においては地域の特性に合わせた独自の行事が生まれました。